Created on October 2, 2018





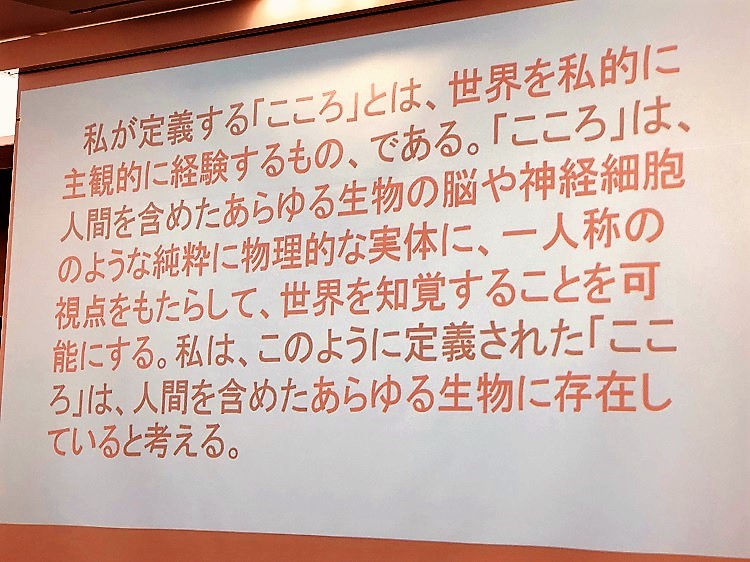



パネルディスカッション 2020年大学入試問題を乗り越える思考力
続いて、「2020年大学入試問題を乗り越える思考力」と題し、静岡聖光学院の植田克彦先生、聖学院中高の児浦良裕先生と本橋真紀子先生とのパネルぢスカッションが行われました。コーディネーターはスタディエクステンションの鈴木裕之先生です。

このセッションでは、このシンポジウムの並行して行われた小学生対象の思考力セミナーを振り返り、2020年大学入試改革で求められる思考力とは何か、ニュートンやアインシュタインのように、思考力が育つ学びとは何かを議論しました。
まず、植田先生が思考力セミナーの企画意図を説明しました。今回の算数の思考力セミナーのテーマは「包む」。静岡伊勢丹とのコラボレーションで生まれた企画とのこと。「包む」行為とは神様へお供えする行為の一環であり、大切なものを守ることを指します。この「包む」行為を通して、数学的思考を楽しもうという趣旨だそうです。

まずは、折る素材を色々見てもらいます。そののち、なるべく無駄なく包もう、エコに無駄なく限られた紙で包もうと語り掛けます。そのさい、紙を切らず、一枚で包むことが条件として与えられます。レベルは3段階。レベルアップするごとに紙が小さくなっていきます。
そして、レベルに合わせたものの置き方があるそうです。ある角度でないと包めない。例えば、傾ける角度18.43493度、タンジェントでないと包めないものが含まれていたそうです。

こうして、実際に包み紙を折りながら角度の重要性を学んでいきます。そして、こうした折り方は私たちの生活の中でも活用されていることに触れます。「ミウラ折り」「ハサミムシの羽」「ビールの缶」「人工衛星」など、興味深い探究ワードが数多く示されます。最後は、振り返り。200字程度でまとめ、楽しい授業を整理し、締めくくりました。

鈴木先生は「子どもたちが楽しそうに包む姿が印象的だった」と思考力セミナーの感想を述べたのち、これはSTEAM教育の一つの姿だと指摘します。包み紙を折る作業は、まさにArtであると。
この話を受け、児浦先生はSTEAM教育が学びの場を活性化させると述べました。紙を折る行為はまさにArtであり、レゴシリアスプレイ(レゴを使いながら、創造性を育み、人と組織の変革をもたらすプログラム)に通じるところがあるといいます。
今回の思考力セミナーで行った最初のワークで「どんなものを包む?」と生徒に尋ねたさい、反応はそうでもなかったといいます。しかし、振り返りのワークはほぼ全員が枠一杯に文章を書くようになったそうです。手を使うことによって、脳が活性化し、思考の段階が言語化した様子がよくわかると、児浦先生は感想を述べました。
ここで鈴木先生は「数学は答えがある、そして正解にたどり着かないと不安になりがち、日本の教育はそうなりがちだ」と言及し、今回のセミナーは失敗しても怖くないというマインドセットがされていたと指摘しました。
他方、鈴木先生は海外ではどうなのかと、本橋先生に尋ねました。本橋先生は、海外の数学は公式があらかじめ示され、どれを使うかは本人の判断による、と紹介しました。一方、日本では公式を覚えなければなりません。他方、日本の数学の教科書はよくできているから、無駄がないと指摘します。生徒から見ると無機質である、と。そして、数学は歴史、営み、成功失敗体験の積み重ねがあるにもかかわらず、捨象されていることに言及しました。

このように捨象されがちな学びを取り戻そうと腐心しているのが、児浦先生と植田先生です。単元の初回は教科書から一度離れ、数学の面白さを感じるような仕掛けを入れるそうです。生みの苦しみがあるが、教科書の余白にも力を入れ、生徒の思考を促進する工夫をしているそうです。
また、2020年大学入試改革で求められる思考力についての話になりました。本橋先生はものの見方という切り口で、「私たちは立体を外から見るが、ミウラオリの三浦さんは内から見ていた」といいます。数学は図形的な見方、代数的な見方 多様な見方があります。一つの解にたどり着くのにはさまざまなプロセスがあり、その方法を学ぶ教科であるし、数学は2020大学入試改革の土台になる教科だと述べていました。
児浦先生は「思考の手順として『情報をインプットする』『考える』『アウトプットする』という3段階がある」といいます。この過程で言語化が行われるわけだが、男子はなかなかことばが出ず、女子は出やすいという特性が感覚的にあるそうです。その点、数学は言語ではなくて、非言語のものを扱って、手を使って表現できる教科であるとのこと。具体と抽象の行き来をしつつ、例えば式で表現できなければ表で、と思考と表現能力を育成できる学問が数学だといいます。
植田先生は答えを早く出すことが求められていた時代はすでに終わり、「思考のプロセスが大事」と強く述べました。答えに至るまでのどう考えたのか。今回の思考力セミナーで言うと、包むためにどういうプロセスを踏んだのかが大事。たくさんの失敗が土台になるし、色々粘り強く考えることが大切だといいます。
ここで、鈴木先生は話題を変え、東京大学理科Ⅱ類の小論文の入試問題に触れました。
「人間以外の生物に「こころ」は存在するか」。そして、ケンブリッジ大学に合格した生徒が書いた答案(パワーポイント4枚)を提示しました。
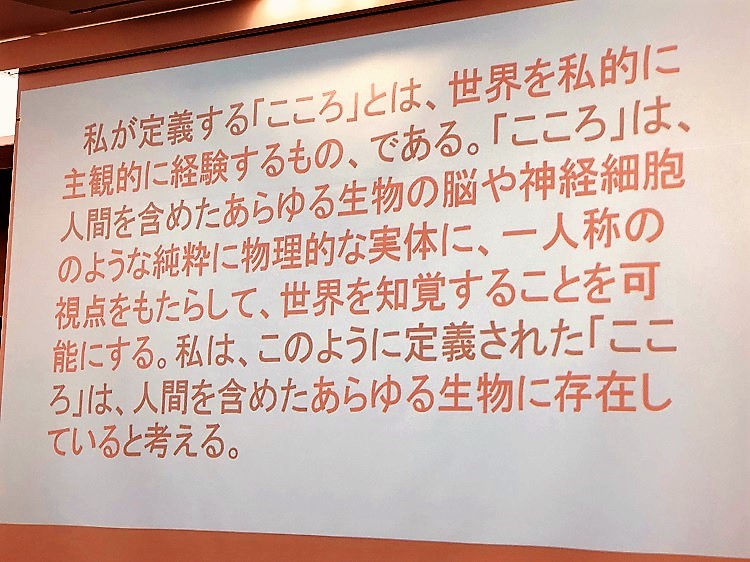
筆者が読む限り、様々な対話の末に執筆したことがよくわかる答案でした。日本の普通の高校生とは歴然とした差があることは、一読すれば明らかです。鈴木先生は、ケンブリッジ大学の入試は面接官との対話が含まれることに言及しました。答案を執筆した生徒と「答案がうまくないのは問題が悪いか、もしくは対話が悪いかだ」「いかに対話を楽しむかだね」と対話したことを明かし、思考のプロセスが大事だと指摘しました。
そして、この生徒は主体的に学んでいた形跡があるそうです。例えば、1本のドラマを見るのに5時間かけるそうです。用語が出てきたら止め、調べて先に進む。結論を急ぐのではなく、プロセスを大事にしている様子が伺えるエピソードです。
植田先生は、こうした論文と数学的思考力との関係性について考察しました。この論文ではあなたの考える「こころ」を定義することに触れ、数学では定義は大事だと共通点を指摘しました。言葉をうまく定義をしたということは、数学をうまく学んできたことに通じ、上手に論理が展開できるといいます。
ここで、来場なさっていた三田国際学園中高の田中教頭が飛び入り参加。

「自ら主体性を持つからこそ、あのような学びを得たのだろう」と述べました。与えられた問いであっても、機械的に論述した答案と、自ら思考を繰り広げる答案は雲泥の差が生じます。筆者は、ここに日本と海外の大学教育、そして入試の在り方の違いの一端を見ました。思考のプロセスを丁寧に見ることができ、探究や研究の世界への耐性やポテンシャルを測ることができる論文を重視するか否か。
そして、そうした大学教育に向かう力を高校で養えているかどうか、というクリティカルな問いを学校や教員は持つ必要があるのではないかと感じた瞬間でもありました。
最後に、ニュートンやアインシュタインのように、思考力が育つ学びとは何か、ディスカッションが行われました。
児浦先生は「どの子も才能がある」と述べます。でも、誰かが設けた枠によって芽が出ない。我々は蓋を取り払い、また、蓋を自らの力で突き破ることを期待していると熱を込めて述べます。そして、こうした学びを経ると、中学3年生くらいになって自信過剰となるそうです。
そのとき、外界に触れることが大事であるといいます。他の子たちと交流する機会を設け、自己が勝手に立てている壁を取り払う。その様子を、聖学院ではクエストカップで優秀な成績を残した生徒さんを例に語りました。他流試合で女子にコテンパンにやられ、やられぬかれて、自己を確立していった様子が目に見えるようでした。
本橋先生は自らの「子ども」に対する認識について語りました。当初、思考力セミナーを実施するにあたり「子どもは難しいのでは」と思っていたそうです。しかし、それは間違っていたし、いまでは楽しく思っているといいます。教員は得てして「無理だ」「難しい」と考えてしまいがちですが、子どもたちは突き抜けてくれるし、その瞬間を共有することが楽しいそうです。私たち大人は子どもたちに制限をかけてはならないし、ニュートンもアインシュタインも、大人が天井をつくっていたらここまで才能は開花しなかっただろうと、語り掛けました。
植田先生は「『間違いじゃないの?』ではなく『なぜそういう答えになったの?』と尋ねることの大事さ」を説きます。色々な意見の中から新しい意見が出るものであり、洗練された日本の教育はプロセスを欠いていると実感しているそうです。教科書の中にある道具を一度横に置き、自分で考えて取捨選択することの大切さがあると述べました。
ただ、残念ながら、一般的な学校では成績や偏差値という物差しで子どもの良しあしを査定する世界が繰り広げられています。そうした中で、21st CEO加盟校のように、思考のプロセスを尊重する学び、そしてその思考を促す教師の存在が、誰一人として子どもの才能を取りこぼさない学校づくりには欠かせないといえるでしょう。
ファイナルセッション イートンで学ぶ
そして、最後のセッション「なぜ静岡聖光学院か」では、イートンサマースクールに参加した生徒と、ご担当の渥美行規先生とのトークセッションが行われました。渥美先生は寮の担当であり、英語の先生です。国際交流の担当でもあり、初めてイートンサマースクールに参加したそうです。

そして、生徒さんの軽妙なトークが始まりました。もともと海外への興味があり、イートンの魅力に憧れてサマースクールに参加したそうです。特に印象に残ったのは、キングススカラー(イートンの中のエリート)との対話とのこと。
彼は日本文化にも精通し、「芥川龍之介『鼻』についてどう思うか?」と尋ねられたそうです。しかし、深く語り合えない自分がいたといいます。自分は日本のことを知らない。彼は英語を勉強しようと推奨しているなかで、自国の文化を知らないで行くのはどうなのかという問題意識を抱いたといいます。

その経験から、自国の文化・習慣を理解すること、相手の文化・習慣を比較しながら、異文化理解・国際交流を重ねていきたいそうです。そして、彼は今後の活動を意思表明しました。来年はインターナショナルサミットにかかわっていきたいと述べ、海外の高校生たちと協働したいと決意を述べ、英語のアドリブで会場を沸かせました。
渥美先生は「世界の未来を憂い、そして身近なところから変えられる未来はあるし、21世紀型教育機構にはそういう学びの場がある」と述べました。
最後に、静岡聖光学院副校長の星野先生は「静岡ではどこにも負けない私学に成長する」「世界にも通用する静岡」「静岡から世界をつくる」「生徒のために、世界のため、日本のため、そして静岡のため」と熱く語りかけ、会は盛況のうちに終了しました。
静岡聖光学院と聖学院の取り組みを通して、まさに私学としての使命をどう全うすべきかを考えるシンポジウムとなりました。成果重視の一般的な教育観から脱却し、我々大人が「未来をつくる子どもたちをどう育むべきか」という教育の原点を考えることの重要性を考える機会を得たといえます。
しかも、その使命をポジティブに捉え、日本と海外の中高生に横たわる意識の格差を埋め、日本からどういう教育を生み出し、発信するか。未来を創造する力を身につける大事な機会が中学・高校であり、子どもにとって大事な6年間を選び取ることが非常に重要であることを感じた会でした。