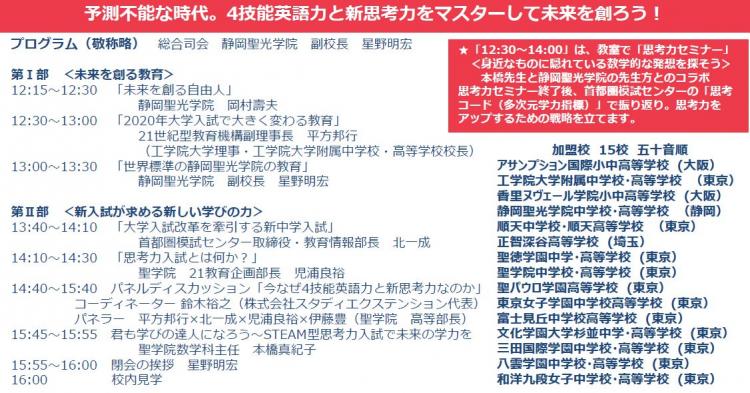富士見丘 教師力相互に磨き、グローバル教育3.0へ挑む!
2018年3月、富士見丘は、SGH認定校として3年目を終え、SGH1期生が卒業した。そして、その大学合格実績は世界大学ランキング1100以内(世界の大学の上位5%)に入っている国内外の多数の大学に進んだ。中でも、ロンドン大学キングスカレッジ(QS世界大学ランキング23位*)、トロント大学(QS世界大学ランキング31位*)、クイーンズランド大学(QS世界大学ランキング47位*)、シドニー大学(QS世界大学ランキング50位*)といった海外の名門大学への進学は、圧巻である。(*世界大学評価機関Quacquarelli Symondsが発表した「2018年世界大学ランキング」。日本の大学は、東京大学が28位、京都大学36位、東京工業大学56位。)
そして、SGHの後輩たちは、今年も、SGH甲子園や模擬国連で実績をあげている。このような成果は、5年目を迎える21世紀型教育を通してでたものであり、SGHプログラム開発とその実践は、中高6ヵ年の同校の21世紀型教育と親和性があったといえよう。しかしながら、富士見丘の教師は、この成果は始まったばかりで、これからもっと飛躍していく。そして、英語力、ICT技術などは、どんどん生徒が教師を超えていくのは火を見るよりも明らかだから、教師も学び続け、SGHプログラムや21世紀型教育のアップデートを行っていく必要があると覚悟を決めている。
そこで、今年4月3日、2018年度の富士見丘の先進的なグローバルな教育をアップデートするために、多様な研修が立て続けに行われたのである。by 本間 勇人 私立学校研究家