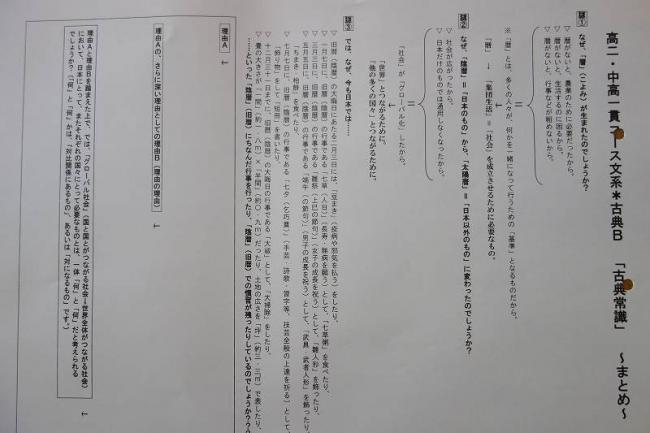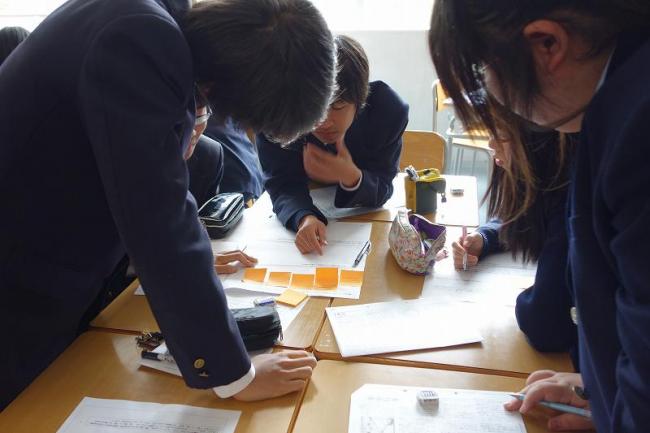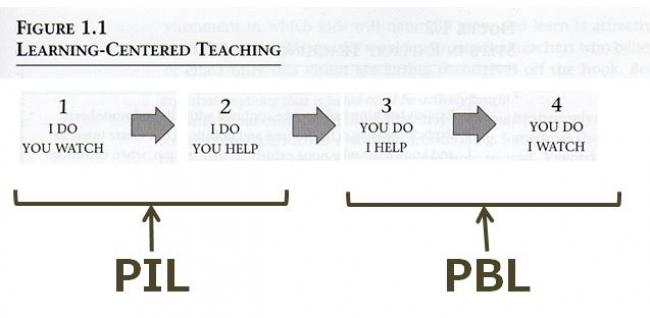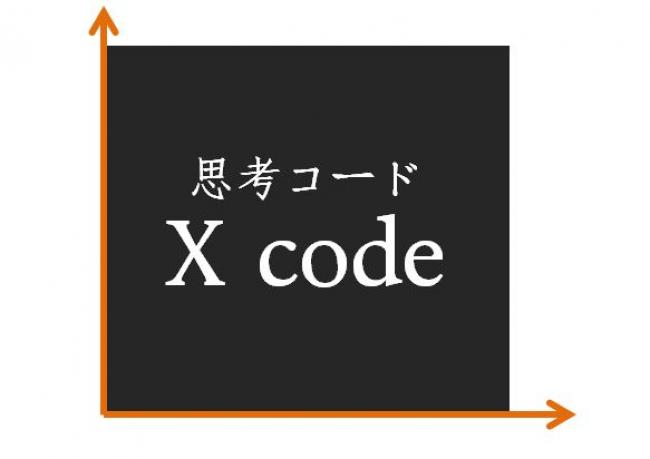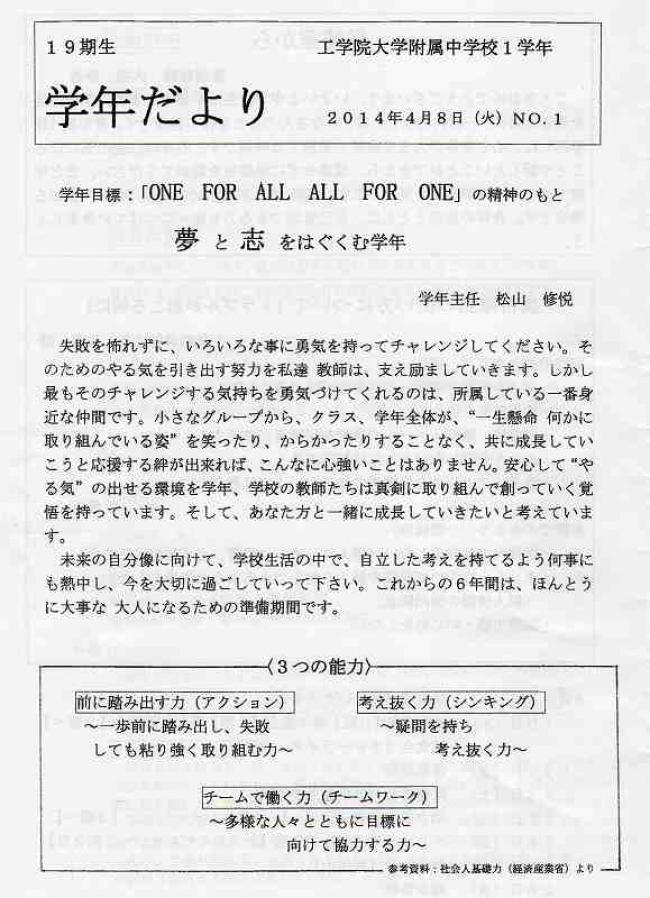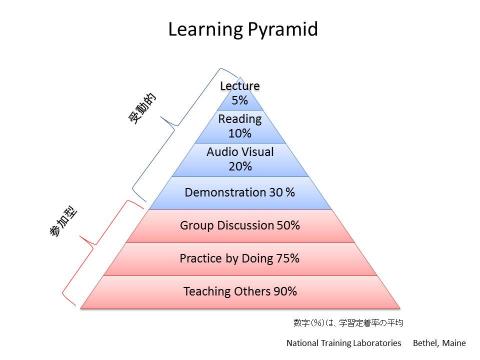第2回 21会カンファレンス 開催 (1)
5月30日(金)富士見丘学園に21会メンバー校の先生方が結集した。都心のビル群が一望できるラウンジで、21会会長で富士見丘学園理事長校長の吉田先生が、静かに、しかし力強い決意とともに、21会と私立学校の精神を語った。 by 松本実沙音 :21会リサーチャー(東京大学文科二類) & 鈴木裕之:海外帰国生教育研究家

開会に先立ち、総合司会の菅原先生(八雲学園)と本橋先生(聖学院)は、21会内部の参加者だけでカンファレンスを行うことの意義について、「21会の考え方、目的、これからどういったことをやっていくのかということを会員校の中で共有していく機会」と位置付け、この日のカンファレンスで経験したことを各学校に持ち帰って広げてほしいというメッセージを送った。そして、会場が21世紀型教育に対する期待感に包まれた中、富士見丘学園の吉田理事長校長の開会挨拶が始まった。

「21会の真骨頂」 吉田晋会長(21会会長・富士見丘学園理事長校長)
全体挨拶において吉田先生は、特別な催しを行うときに利用するペントハウスラウンジに21会校のメンバーをお招きすることができて大変嬉しいと率直な気持ちを真っ先に表現した。21会校メンバー校を身内として歓迎したのだ。そして身内だからこそ話せる本音で語ってほしいという思いも同時に表明した。
中教審の委員でもある吉田先生は、これまで公立の学校に様々な提言をしてきた経験から、21世紀型の教育はやはり私立学校でしかなしえないことであると痛感している。どれほど制度改革が行われても、理念や継続性のないものは、結局最後にダメになってしまう。そうした思いから、私立学校、そして21会という有志が強く連帯していくことへの期待を表明したのである。

自分だけ、自校だけという精神は、学校の本来的な姿ではない。21世紀の社会を考えれば、私たち自身が持つべき価値観が教育内容として問われてしまうのだというメッセージである。私立学校が6年一貫教育やグローバル教育などにおいて公立のモデルとなってきたことを誇りとしつつ、これからは私立学校全体がより高め合っていく関係を構築していくことの必要性を訴えた。

21世紀型教育を推進する自分たちがまずは開かれた価値観で連帯していこうとするところは、まさに吉田先生が21世紀私学人たる所以である。
この場に集うメンバー校の想いを確認するところから、第2回21会カンファレンスは開始された。