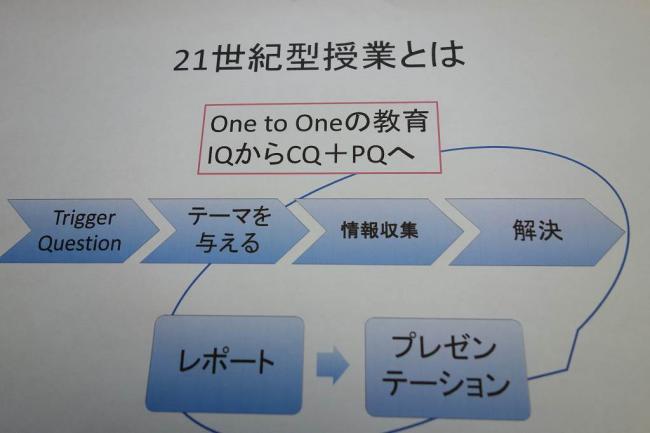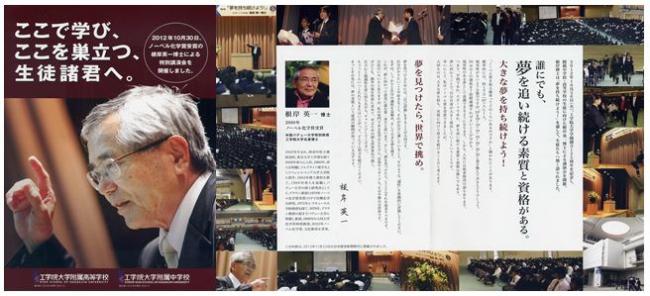テクノロジーとマーケティング、コラボレーションの総合力が、2025年以降の世界の新しい仕事を創り出すと言われている。この2つの力を表現するときに世界共通言語として英語を学ばざるを得ない。イノベーション教育とグローバル教育、そしてその根底にリベラルアーツ。
これが正しいグローバル人材育成の世界共通のビジョンである。しかし、現状の教育で、テクノロジーという意味でのイノベーション教育を中等教育段階で十分に行うことは難しい。米国でも、2015年までにオバマ政権は教育政策の一環として3Dコピー機まで備えたメイカーズスペースを1000校につくる構想を進めているぐらいだ。きちんとプランを立てなければ実行できないビジョンなのである。
ところが、工学院は、明治開校以来、テクノロジーの才能を専門に育成する教育機関であり、その伝統は今も脈々と続いている。自前でそのプランを実行できる稀有な教育機関である。
テクノロジーはスキルの側面のみならず科学的なものの見方や考え方も共にするものであるが、そのリベラルアーツ的側面を切り取って、近代は暴走してきた経緯も記憶に新しい。
そこで、昨年125周年を迎えた工学院は、自然と社会と精神の循環をベースにしたテクノロジー教育を展開することを改めて確認し、10000人規模の参加者が集まる「理科教室」を「科学教室」という名称に変えて、そのビジョンを子どもたちと共有するイベントを開催した。(by 本間勇人:私立学校研究家)