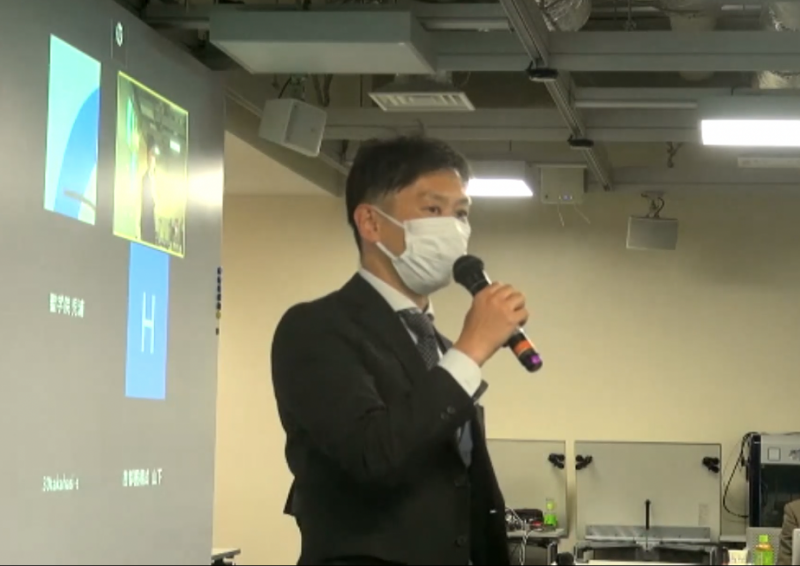2022年度第2回定例会が開催されました(1)
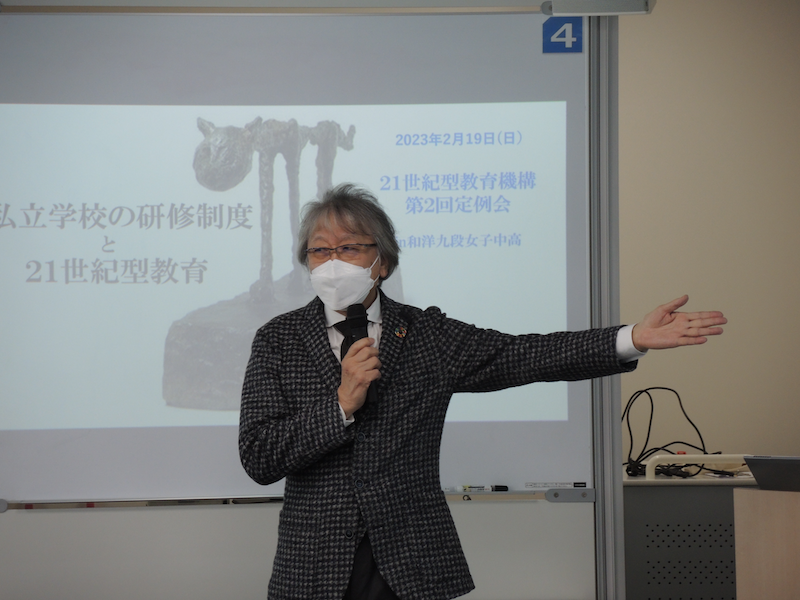
2023年2月19日(日)和洋九段女子中高のフューチャールームに21世紀型教育機構加盟校の校長やマネージャーが集まり、2022年度の総括となる第2回定例会が実施されました。昨年の4月末に第1回の定例会を開催してから9ヶ月半ぶりの開催となります。
今年度の総括という意味合いだけでなく、次年度の方向性を宣言する意味合いもある定例会です。その冒頭挨拶で平方邦行理事長は、1889年、1989年、そして2089年に至るいくつかの重要な年号を示し、地球の未来を見据えて教育に携わることの意義を訴えました。
変革の時代には過去と決別していくことが求められることを、20世紀初頭の前衛芸術における潮流を参照しながら確認し、さらに幕末における私塾の歴史やバカロレアの入試問題に言及し、硬直した現在の教育を打破する糸口を提示されました。