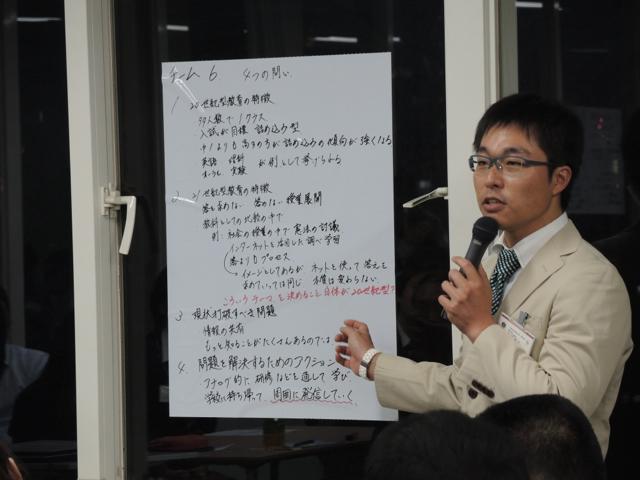八雲中1 World View プロジェクト型学習始まる
6月14日(土曜日)、八雲学園の中1のレシテーションコンテスト開催。入学してから2か月半が経過した中1にとって、英語教育の八雲の本格的な行事がいよいよスタートしたことになる。
八雲学園の行事は、1つひとつ完結していながら、実は6年間すべて意図的・計画的につながっていて、授業で知識を、行事で知識に息吹を与える感性を育てる。それゆえ、近藤校長は、この八雲の教育全体を感性教育と呼んでいる。
レシテーションコンテストは、もちろん英文を読み・書き・聞き・話すという4領域全体をカバーしているが、さらに深い仕掛けがある。by 本間勇人:私立学校研究家